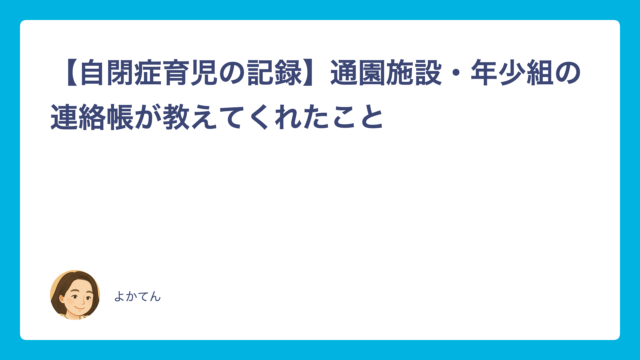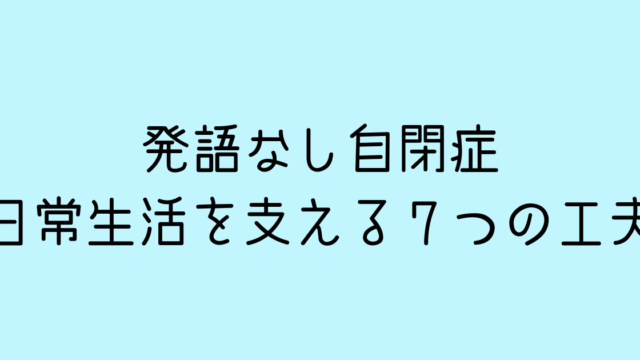みーちゃんの“こだわり”とスタディクロックがつなぐ時間の感覚
数字の意味は、まだわかっていない。
でも、「数字が書かれているもの」には、なぜか強く惹かれるみーちゃん。
テレビのチャンネル、電子レンジの表示、エレベーターのボタン、テレビ通販の電話番号。
数字があると、いつもじっと見つめてる。
それを見ていて、ある日ふと思った。
「数字に興味があるなら、“時計”がいいかもしれない」
時間の理解までは難しくても、針の動きと数字の関係を“図”として覚えることはできるかもしれない。
そんな期待を込めて、リビングに置く時計を探した。
そして、出会ったのが――
くもんのスタディクロックだった。
時計を「読む」のではなく、「見る」みーちゃん
みーちゃんは、数字の意味を理解していない。
けれど、くもんのスタディクロックのように分の数字がすべて表記されたデザインは、
彼女にとって“理解できそうなもの”として目に入ったようだった。
普通のアナログ時計は、「1が5分」「2が10分」…とルールを覚えなければいけない。
でも、この時計は、“5・10・15・20…”とすべての「分」が見えるように書かれている。
それだけで、親が伝える負担も、子が理解する壁も、ぐっと下がった気がした。
“8時”の意味はわからなくても、“針の位置”なら伝わる
みーちゃんは今も、「8時になったら○○しようね」と言っても反応がない。
けれど、「針がこの位置に来たら歯磨き」と伝えると、行動につながるようになっていった。
そして最近では、アレクサが歯磨きのリマインドを案内する時間を、時計の針の位置と重ねて覚えているようで――
その時間が近づくと、自分からスマホを置いて、静かに待機することも増えてきた。
まるで「来る」とわかっていて、先回りして準備しているような姿に、驚かされる日もある。
時計が“生活のガイド”になるということ
- 「このへんに針がきたらご飯」
- 「この角度がお風呂の時間」
- 「この針の位置でテレビはおしまい」
そんなふうに、日常の“流れ”を形にしてくれるのが、スタディクロック。
もともとは“知育時計”として売られているけれど、
我が家にとっては視覚支援のひとつとして、なくてはならない存在になっている。
🛒 わが家で使っているのはこれ
▶ くもんのスタディクロックhttps://amzn.to/4kWfKkT
・すべての「分」が数字で書かれている
・針の色や太さが視覚的に分かりやすい
・音も静かで、感覚過敏の子にもやさしい
🎁 おまけ:みーちゃんのこだわり
食後、みーちゃんはいつもスタディクロックの前へ。
スマホでYouTubeを流して、お気に入りの音楽に合わせ、体を大きく左右に揺らす。
その時間はだいたい20分ほど。
なぜ“時計の前”なのかは、正直わからない。
でも、他の場所ではダメで、必ずその場所。
針の動きと音楽と体のリズムが、ぴたりと重なっているように見えることもある。
それもまた、みーちゃんの大切な“こだわり”。
今日も時計の前で、ゆったりとした安心の時間が流れていく。
🪴しめくくり
「時間を教えたい」と思って始めたことだったけれど、
今では、「時間を一緒に感じる」という関わり方に変わってきた。
わかりにくいものは、わかりやすくする。
それだけで、みーちゃんの世界はすこしだけ広がる。