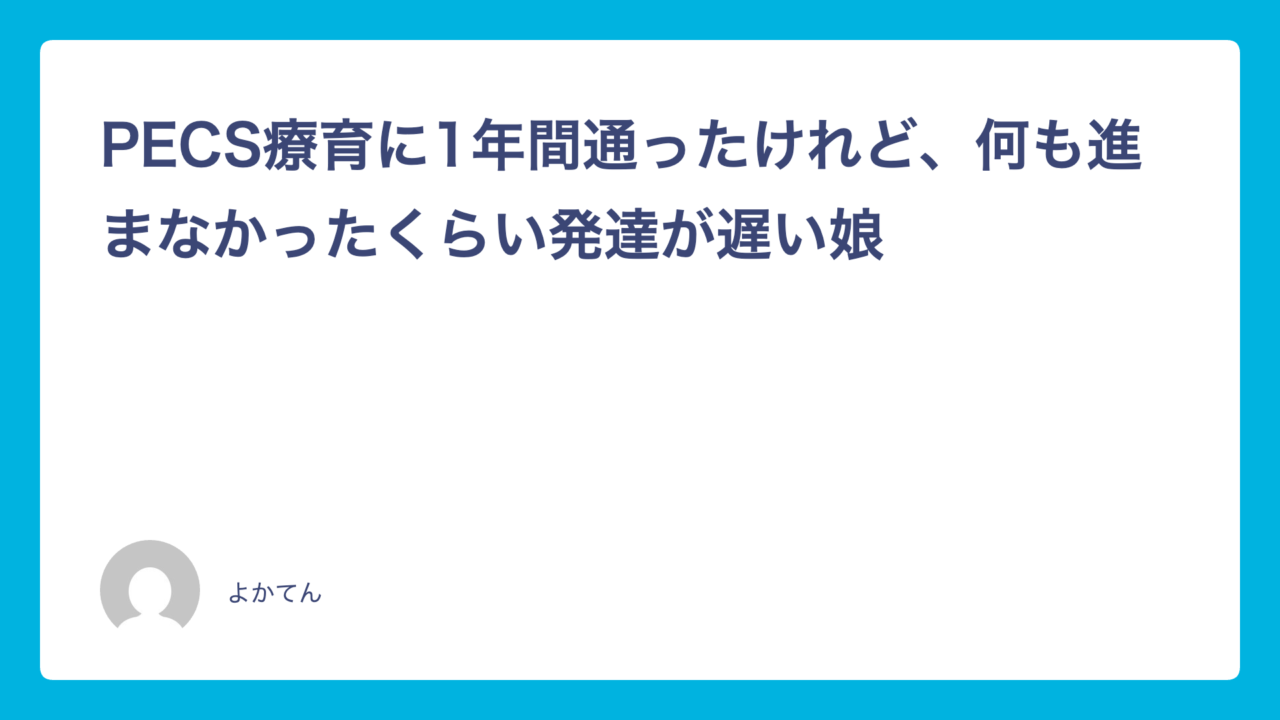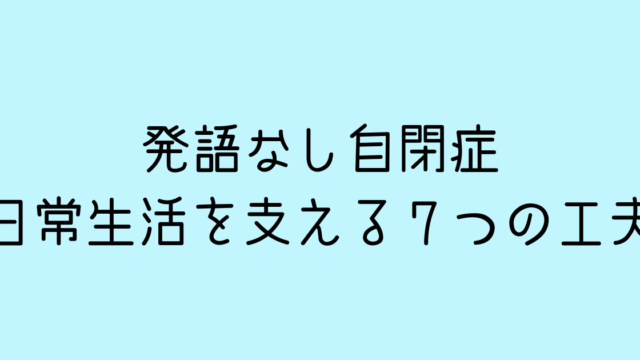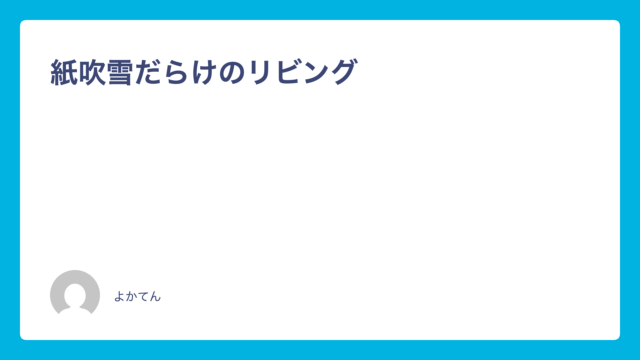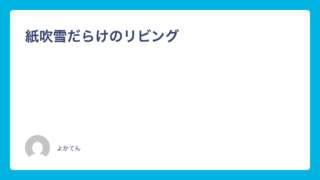娘が3歳のころ、PECS(絵カード交換式コミュニケーション)の療育に通っていた。
民間の療育施設で、隔週40分、みーちゃんの場合は指導員さん2名体制で行われていた。(普通は指導員さん一人)
当時の私は、「コミュニケーションの糸口がつかめるかもしれない」と、わずかな希望をかけていた。
初回の療育の流れ。
- 「あそぶ」のカードを渡す → 指導員さんと遊ぶ
- 「おやつ」のカードを渡す → おやつを食べる
- 「トイレ」のカードを渡す → トイレに行く
この3つのカードを使い、40分間の中で同じ流れを繰り返していた。
ただ、初めのうちは「自分からカードを渡す」という行動がまったく出なかった。
そのため、1人の指導員さんが娘の背後に回って右腕を持ち、もう1人の指導員さんにカードを手渡すという、完全な2人体制での支援が必要だった。
同じ時期に通っていた近所の同い年の男の子は、数ヶ月のうちにさまざまなカードを自分で選び、「かいものにいく」と言うハイレベルなカードまで使えるようになった。(22歳のみーちゃん、今でも使えない)
一方で、娘は1年間ずっと初期の3枚のカードから広がることはなかった。
見ようとしない。選ばない。渡さない。
カードが彼女にとって「何かを伝える手段」として成立することは、最後までなかった。
また、一番遅れている──そう感じざるを得なかった。
「なぜこんなに違うのだろう」
「うちの子だけが止まってしまっている」
その思いは想像以上に重かった。
療育の場では、みーちゃんが指導員さんの腕や肩を噛むこともあった。
痛いはずなのに、指導員さんはその瞬間はまったく無反応。
初めはとても驚き、戸惑った。
子どもは手加減がわからず本気で噛むから、声をあげてしまう程痛いはずだ。
なぜ指導員さんは反応しないのか。
「他害行動をした瞬間に声をあげて反応すると、子どもはそれを“反応してくれた”と捉え、他害が正解になってしまう。そうなるとますます行動がエスカレートするから、他害の瞬間は無反応が鉄則なんです」と。
その話を聞いたとき、指導員さんのプロ意識の高さに心から感動したと同時に、申し訳ない気持ちで胸がいっぱいになった。
みーちゃんの行動に対して冷静に対応するプロの姿勢は、療育がただの場当たり的な対応でないことを教えてくれた。
その一方で、自分の子が他害行動を繰り返すことに対するもどかしさや悲しさも、ずっと胸にあった。
結局、1年間通ってもPECSによって自発的なやりとりができるようにはならなかった。
それでも、意味がなかったとは思わなかった。
PECSの療育は「早ければ早いほど良い」とよく言われていた。
療育の先生方もそう言っていたし、私自身もその言葉に励まされていた。
しかし、実際にみーちゃんを見ていると、PECSにも適切な年齢や発達段階があるように感じた。
みーちゃんの発達年齢ではまだ「PECSを使ってコミュニケーションを取る」ことが早すぎたのだと思う。
一方で、親である私の知識習得は早いに越したことはないと実感した。
いつかみーちゃんが対応できる時期になったとき、すぐに使えるように準備しておくことができたのは、今振り返るととても大きな財産だ。
療育がうまくいかないときでも、親自身が学びを続けておくことは、将来の選択肢を広げるために必要なことなのだと強く感じている。
療育には正解がない。
うまくいかない経験も、その子なりの意味が必ずある。
私の経験が、同じように悩む誰かの力になれたら幸いです。