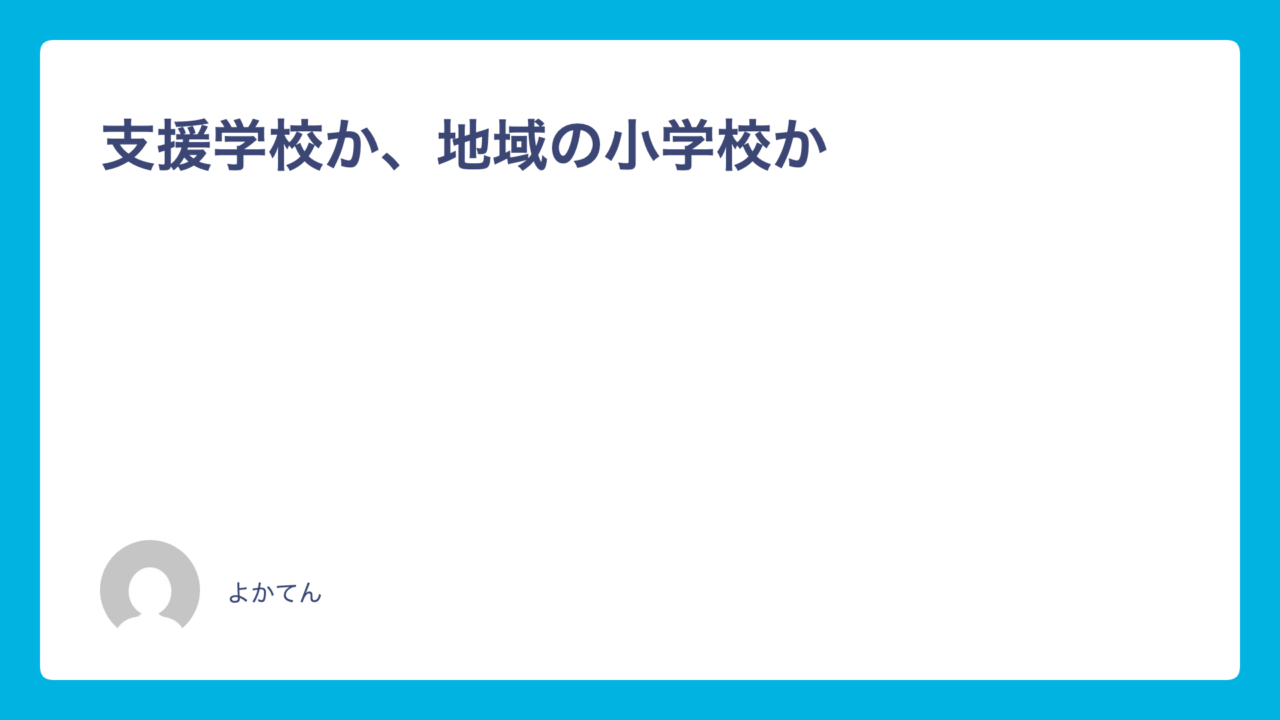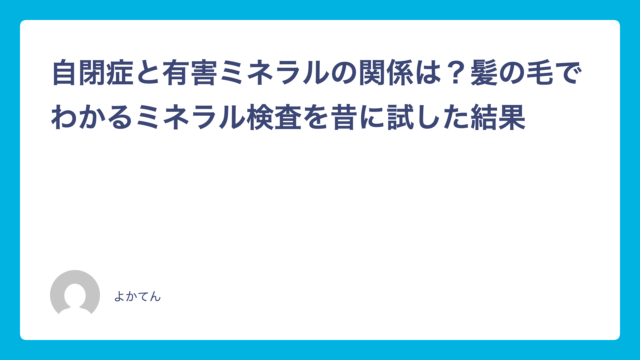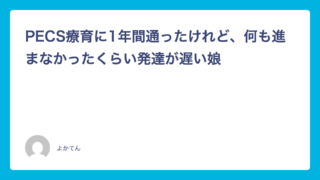通園施設の年長さんになり、卒園まであと少しとなった頃、教育委員会の人を混じえての就学相談がある。
年長さんになってからは、母たちとの話題は進路の話が多くなる。
「どっち(支援学校?支援級?)に行くの?」
6年間過ごす学校だから、みんなすぐに答えが出るはずもない。
でもほとんどの人が支援級を選んだ。
なぜ?
・きょうだい児がいるから、一緒の学校に行かせたい。
・健常の子どもたちとかかわれる機会は小学校しかないから、小学校くらいは地域に行かせたい。
私も同じ意見だ。
進路相談の日。
予想通り、教育委員会の担当者は支援学校をすすめてきた。
娘の発達の状態を見れば、確かに合理的な提案だったと思う。
専門的な支援が受けられ、手厚い人員配置もある。
本人にとって過ごしやすい環境が整っているのは間違いない。
だけど、どうしても地域の学校にこだわりたかった理由があった。
それは、「地域の中で生きていく」ということを、娘にも経験させたかったからだ。
小学校は、地域の人とつながるほぼ唯一の場だ。
中学以降は支援学校と決めていたから、地域の人たちとの結びつきがどんどん薄れていくのは容易に想像できる。
でも、小学校だけは家の近所にある学校に通い、放課後には顔なじみの子どもたちとすれ違い、登下校中に見守ってくれる地域の大人たちがいる日常を送りたい。
娘にとっても、私たち家族にとっても、それがどれほど安心につながるかは言葉にできない。
だから私は、地域の学校を志望した。
たとえその道が、支援学校ほどスムーズではなくても。
かなり大変な道でも、地域で「一緒に育っていく」ことに意味があると信じていた。
相談では、私の気持ちを丁寧に聞いてはくれた。
ただ、支援学校の利点を繰り返し説明され、「お母さん、それでも本当に地域の小学校にしますか?」と問われたとき、正直、心がぐらついた。
「地域の小学校で、何か事故があっても私達は責任取れません。それでも構いませんか?」
とまで言われた。
仰ることはごもっとも過ぎて何も言えない。
それでも最後は、「やはり地域の学校でお願いしたい」と伝えた。
そこまで地域にこだわったのは、地域の小学校の支援級の評判がとても良かったのもある。
学校のスタンスが「支援級あっての普通学級」
支援級の教室が職員室の隣にあり、生徒たちがみんな支援級の前を通って行く。
支援級の前を通る子どもたちは声を掛けてくれるから、浮いた存在にならない。
そして入学早々、授業を始める前に支援級の存在と支援級に在籍する生徒の紹介を一年生にすると言う話を聞いて、ますます地域の小学校に行かせたくなった。
学校によっては支援級は校舎の隅っこにあり、誰も通らないから存在すら知らない子どもがいる、と聞いたことがある。
毎日進路で悩んでいる時、近所に住む教育委員会の上席の方と話す機会があったので相談したところ、「小学校の間は地域がいいと思うよ。みーちゃん、大丈夫だと思うよ。」と言ってくれ、決心は固まった。
就学相談は、制度上は「相談」だが、実際には強く誘導される。
だからこそ、自分の中で軸を持って臨む必要があると感じた。
実際、何度か面談があったが、なかなか地域の小学校を希望と言っても承諾してくれなかった。
そして、2月下旬。
やっと「地域の小学校で受け入れます」と回答がきた。
人員配置の手配など、私が見えない裏側でみーちゃんのために動いて下さった教育委員会の方々に感謝しかない。
これは、もう16年前の話。
みーちゃんの姉が母校で教育実習に入った時、今の小学校の様子を聞いたところ、「今はみーちゃんみたいな重度はいないが、教室が足りないくらい軽度の子どもがたくさんいる。昔とは違う。」と話してくれた。
軽度の子どもが増えたため、重度はもう受け入れ体制がないかも知れない。
実際、小学校を地域で過ごした判断は正しかったのか?
支援学校だと、他害は減ったかも知れない。
もっと落ち着いて過ごせたかも知れない。
でも、今でも近所の公園を散歩したり、マクドナルドで合うと「あっ!みーちゃん」と声掛けてくれて、みーちゃんも嬉しそう。
結論、正解はみーちゃんしかわからない。