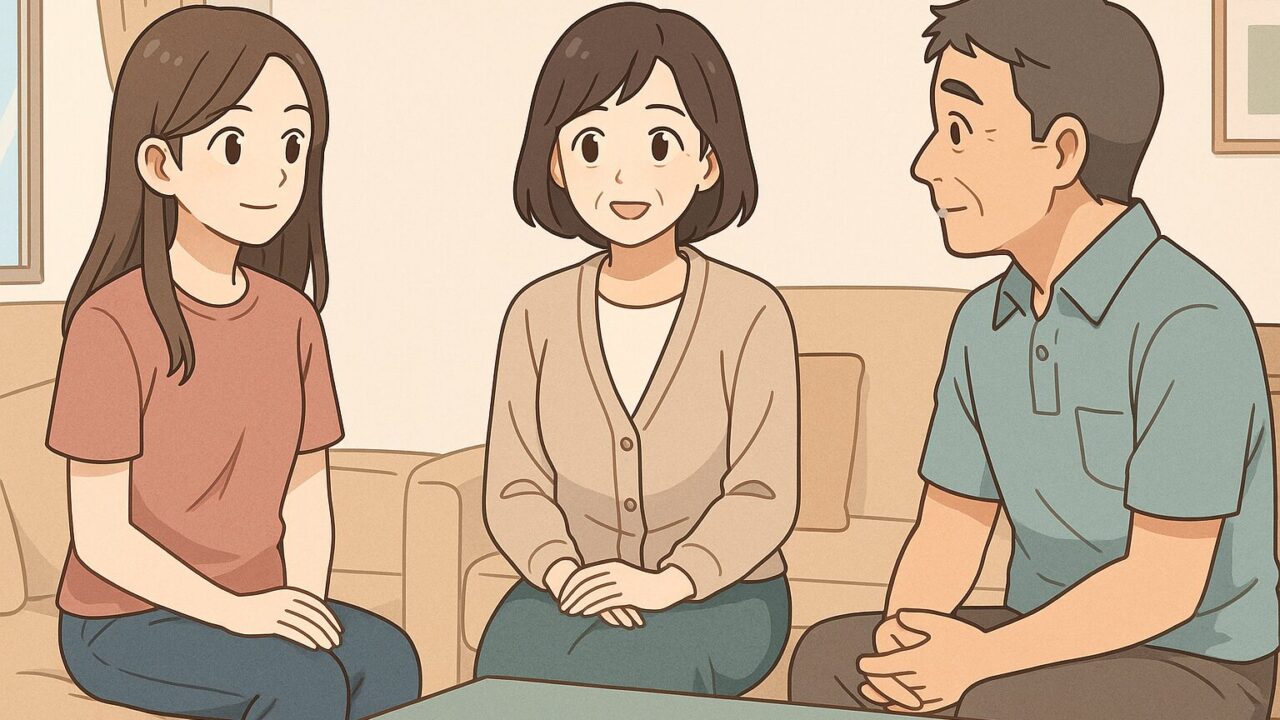ケースワーカーさんが新居に来た日。 まだ住める状態ではなかったので元の家に戻り、長女と元夫に今日のことを話した。
「それなら、私が少し出すよ」──家族の言葉
長女はこう言った。 「おばあちゃんのところに介護に行くのに車が使えないとか、自己破産とか、たくさん規制されて、それでもそんなにもらえるわけじゃないなら、私のお給料から少し出すよ。お願いだから申請は却下して」
元夫も、「知り合いから最近、生活保護の条件が厳しくなってるって聞いてたけど、そこまでとは……。俺も少しなら生活費出せるから、却下したほうがいい」と言ってくれた。
今ごろになって家族が一致団結(笑)。 ありがたいなと思った。私が元夫との生活に疲れて娘たちを巻き込んで家を出たのに、困った時は寄り添ってくれる。 これからも、困った時は助け合える関係でいられたらいいなと思う。
自分で決めた「却下」という選択
それから数日、一人で考えて、結局申請を却下することにした。 私が稼げるようになるまでは、元夫に甘えよう。 その代わり、家事がまったくできない人だから、その分は家事でお返ししようと思った。
ケースワーカーさんに却下の連絡をすると…
翌日、ケースワーカーさんに電話して却下の旨を伝えた。 「電話では受けられないので、窓口に来てください。却下の書類を書いていただく必要があります」とのこと。
療育手帳や住民票の住所変更もあったので、それらもまとめて役所に行くことにした。
窓口で書いた「却下理由」
生活援護課の窓口では、ケースワーカーさんが対応してくれた。 「却下されるのですね。却下して生活は大丈夫ですか?」と尋ねられた。
そうですよね。 生活が苦しいから申請したのに、なぜ却下? ケースワーカーさんが疑問に思うのも当然だった。
「娘が叫ぶとドライブに行かないと落ち着かないのに、車がない生活は無理がありますし、母の通院や介護にもどうしても車が必要です。 事業も少しずつ軌道に乗ってきているので、自己破産はしたくありません。どうすればいいか、もう少し考えたいんです」と答えた。
「今すぐ自己破産ではなく、半年後くらいが目処です。 それと、お母様の通院が理由での車所持は申し訳ないのですが認められません」と返された。
最後に、A4の白紙を差し出され、「ここに却下理由と名前を書いてください。雛形はないので、自由に書いてください」と言われ、簡単に理由を書いて受付は終了した。
思ったよりも厳しかった現実
障がいの特性が理由での車所持が審議対象になるとは、正直予想外だった。 私の周りにも、子どもに障がいがあって生活保護を受けているシングルマザーはいる。 車を所持している人も多い。でも、その子どもたちはみーちゃんよりも軽度。
やっぱり、生活保護を受けずに暮らしていけるように、頑張るしかない。